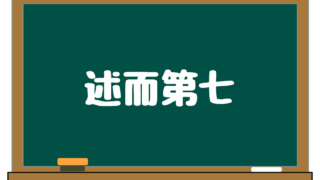 述而第七
述而第七
述而第七08|憤せざれば啓せず、悱せざれば発せず
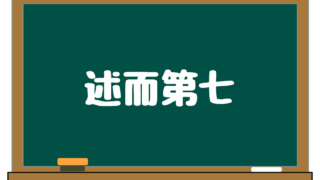 述而第七
述而第七 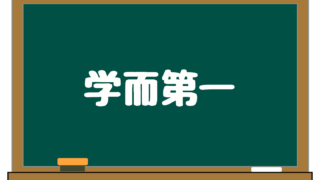 学而第一
学而第一 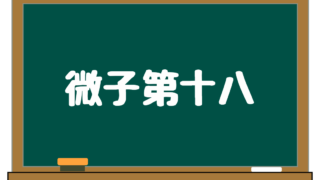 微子第十八
微子第十八 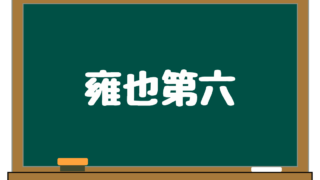 雍也第六
雍也第六 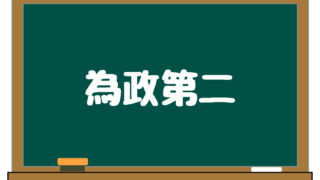 為政第二
為政第二 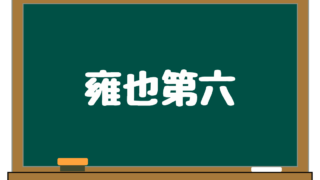 雍也第六
雍也第六 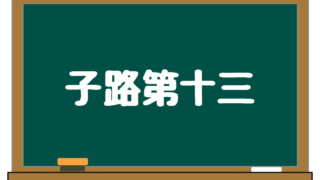 子路第十三
子路第十三 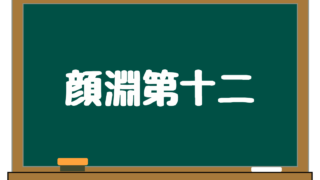 顔淵第十二
顔淵第十二 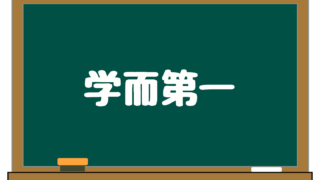 学而第一
学而第一 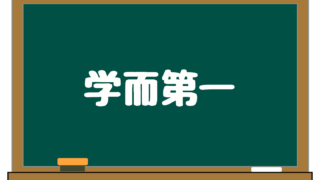 学而第一
学而第一 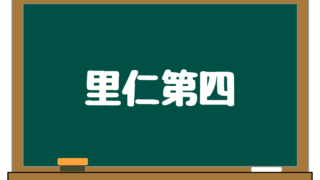 里仁第四
里仁第四 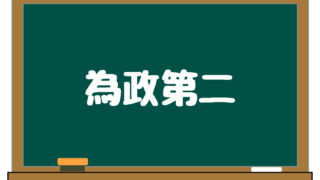 為政第二
為政第二 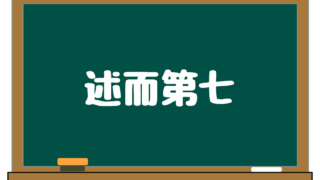 述而第七
述而第七 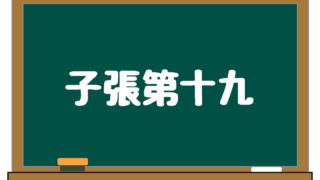 子張第十九
子張第十九 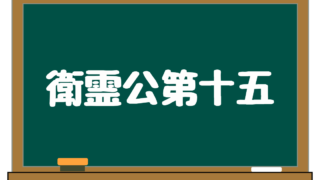 衛霊公第十五
衛霊公第十五 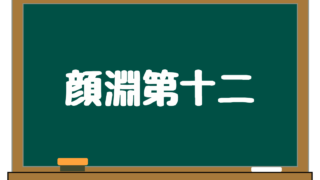 顔淵第十二
顔淵第十二 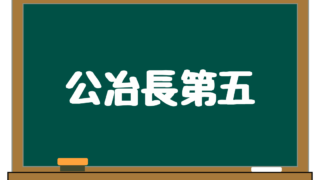 公冶長第五
公冶長第五 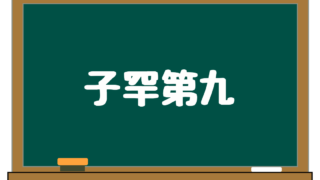 子罕第九
子罕第九 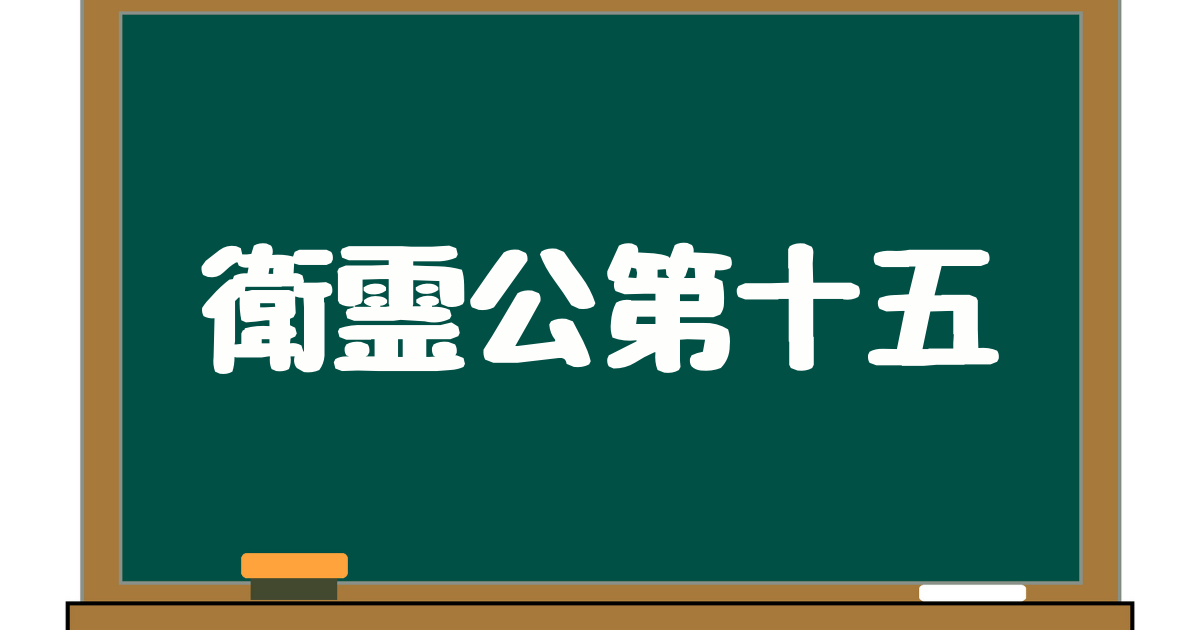 衛霊公第十五
衛霊公第十五 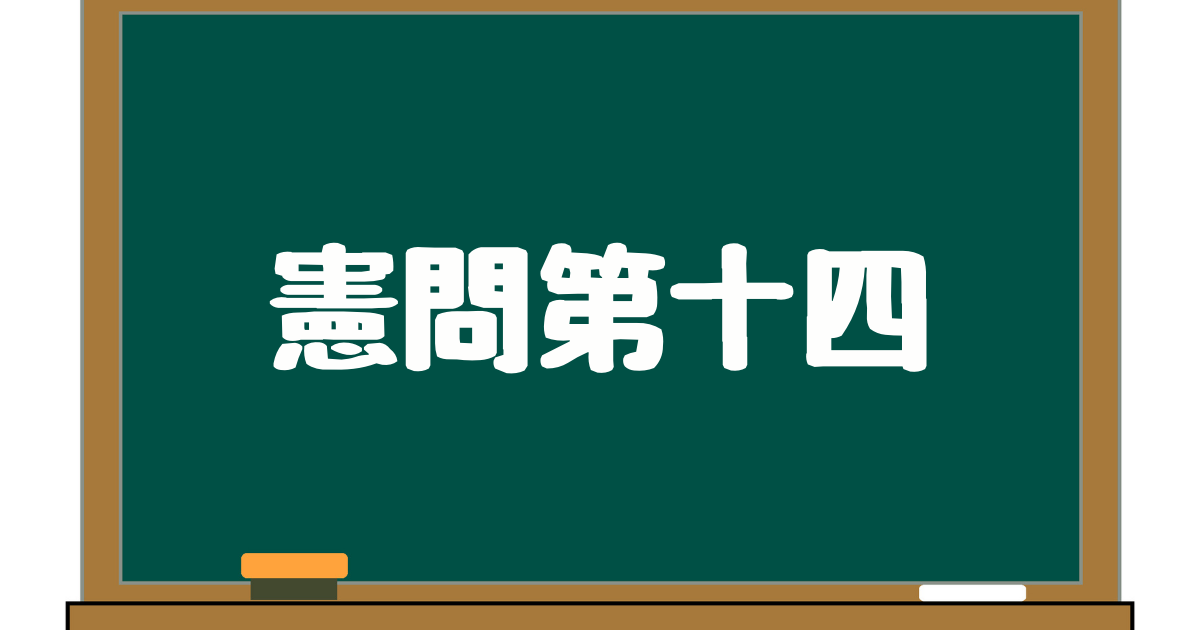 憲問第十四
憲問第十四 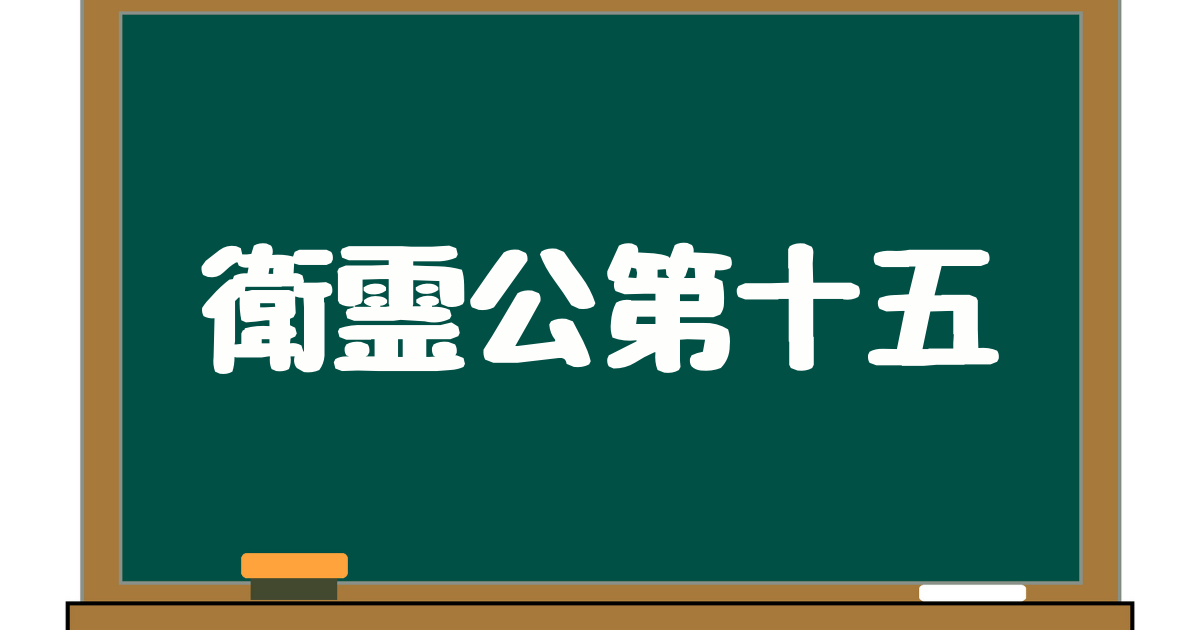 衛霊公第十五
衛霊公第十五 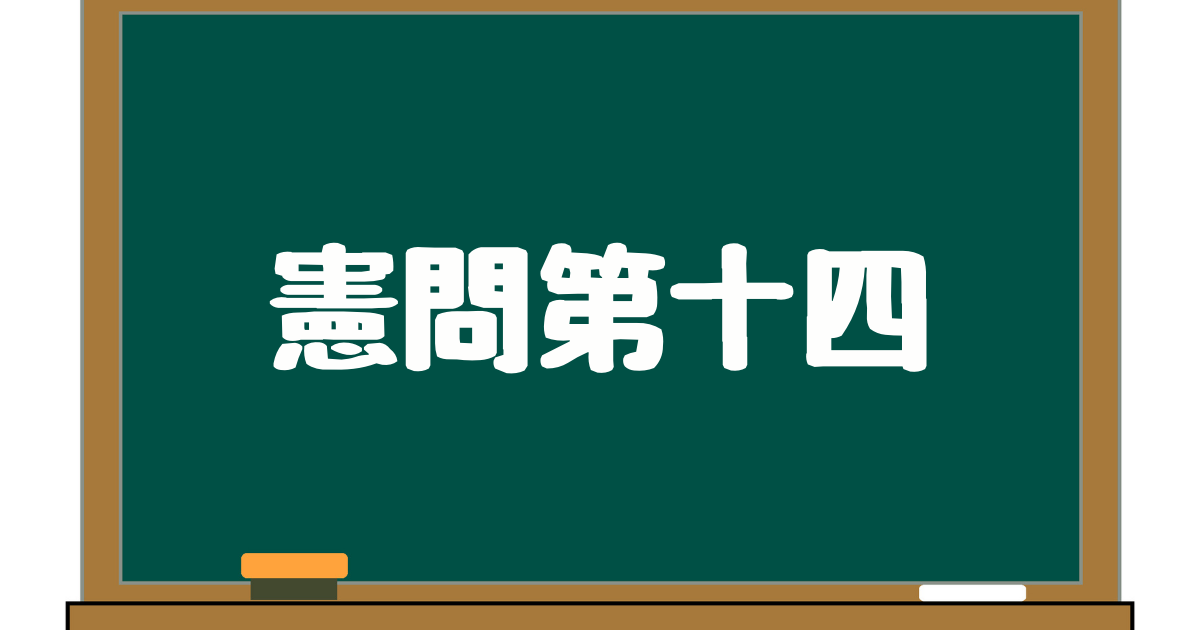 憲問第十四
憲問第十四 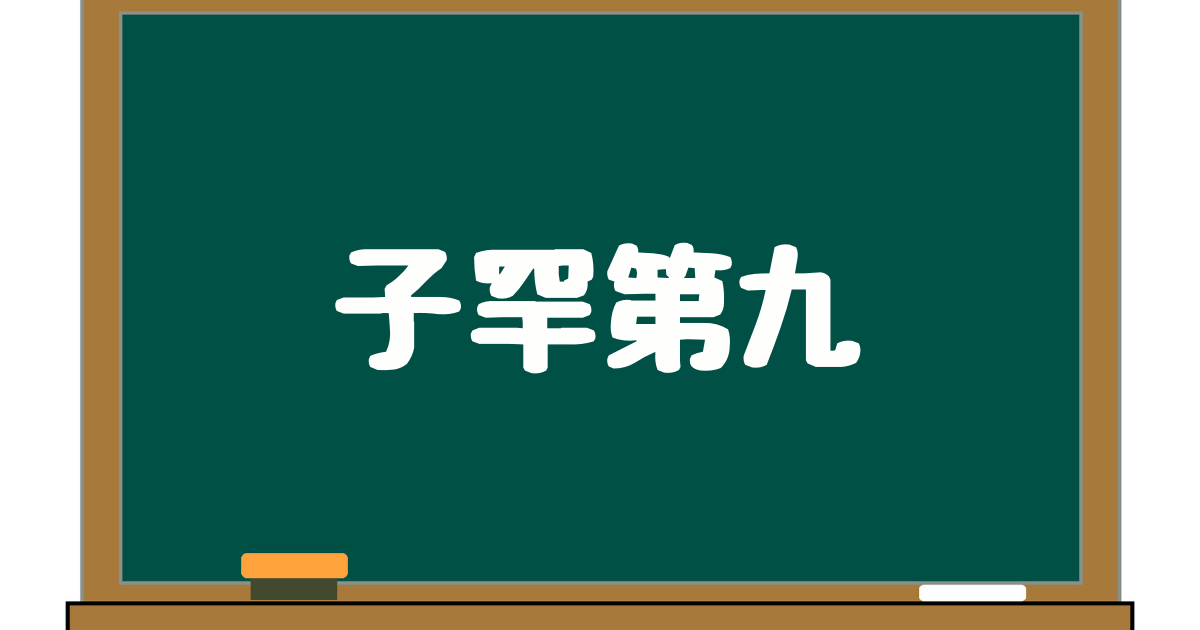 子罕第九
子罕第九 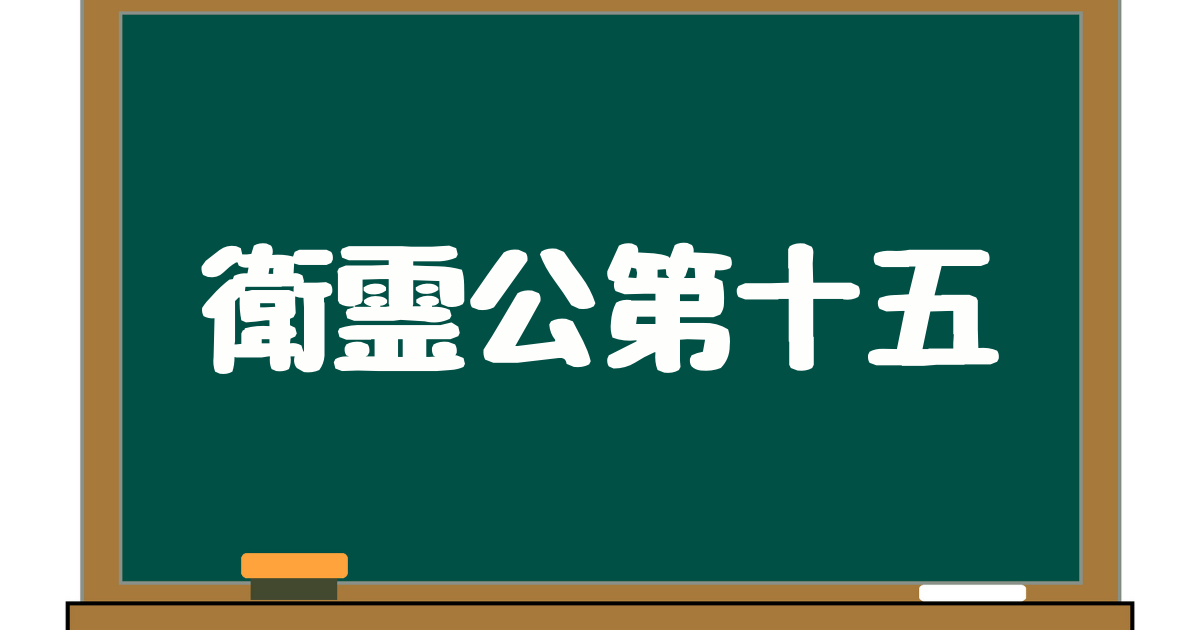 衛霊公第十五
衛霊公第十五 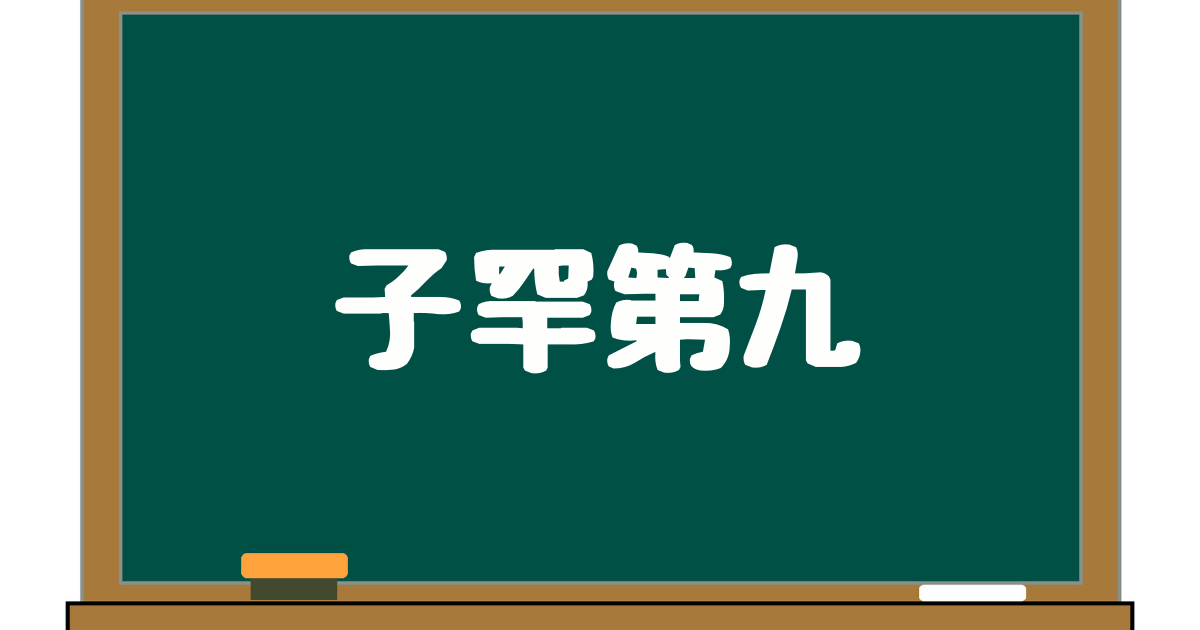 子罕第九
子罕第九 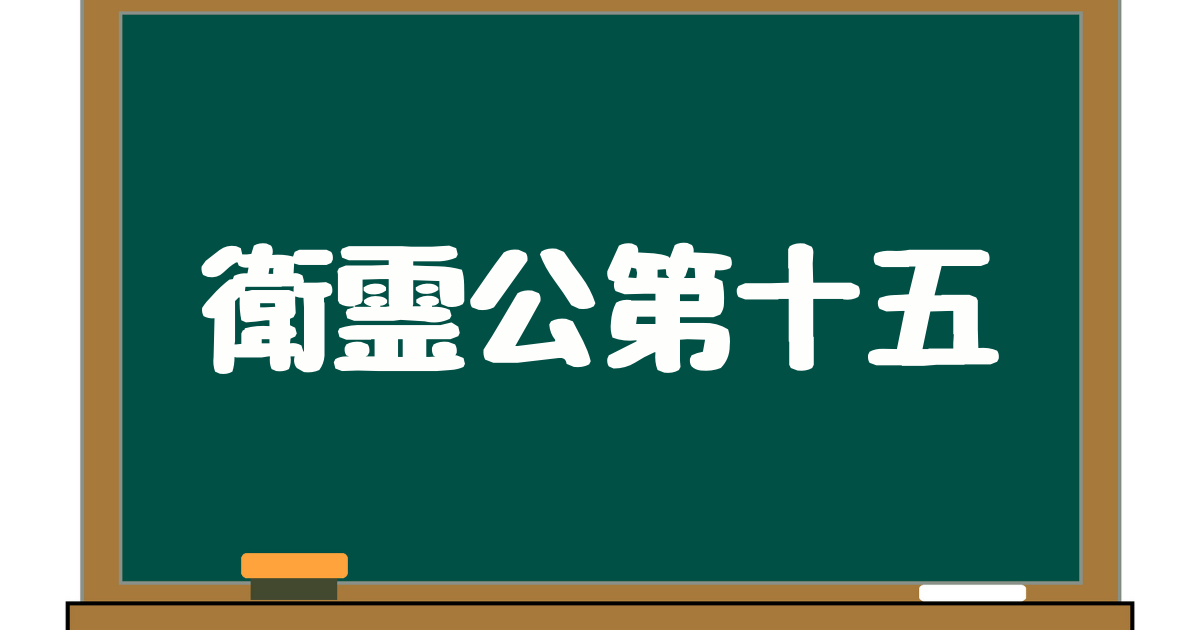 衛霊公第十五
衛霊公第十五 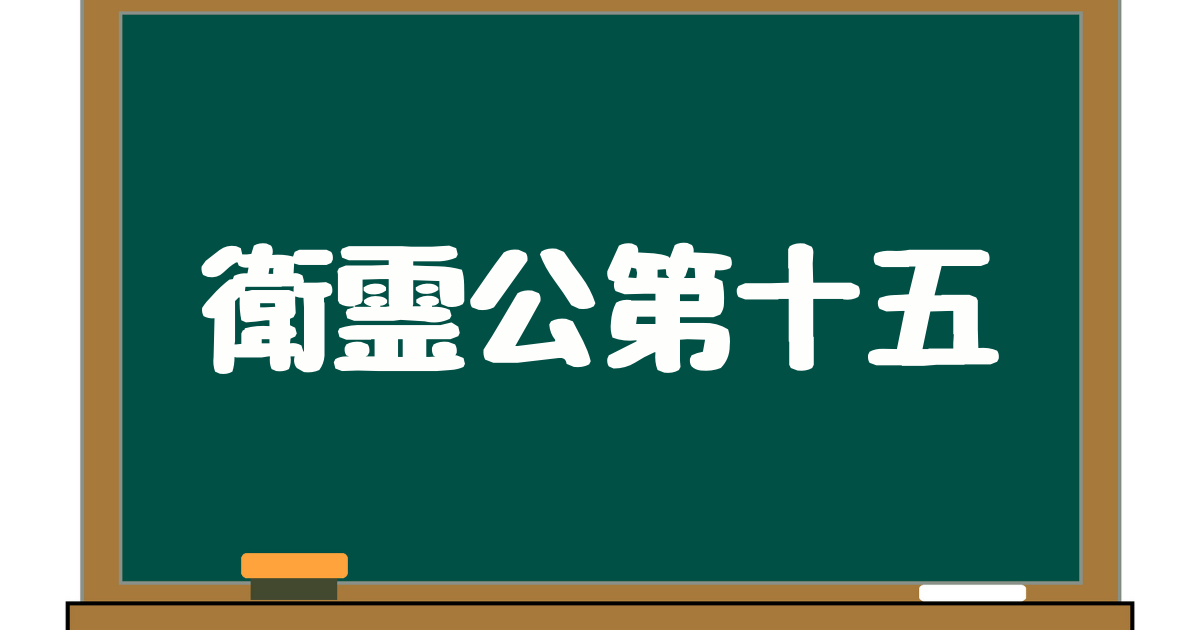 衛霊公第十五
衛霊公第十五 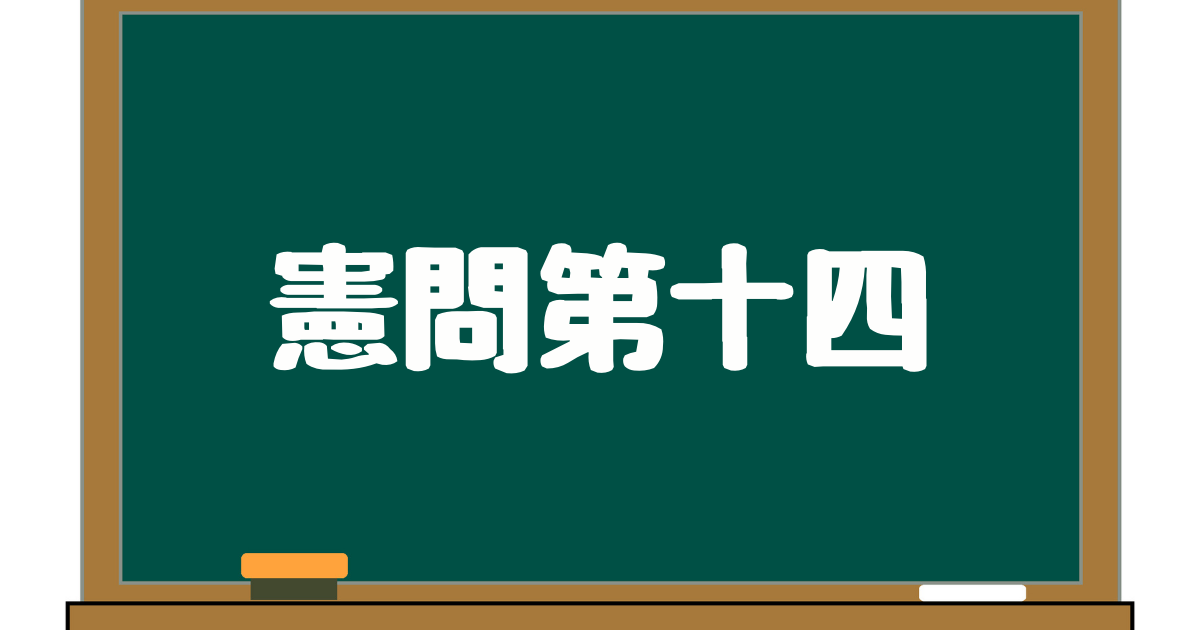 憲問第十四
憲問第十四